-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年10月 日 月 火 水 木 金 土 « 9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
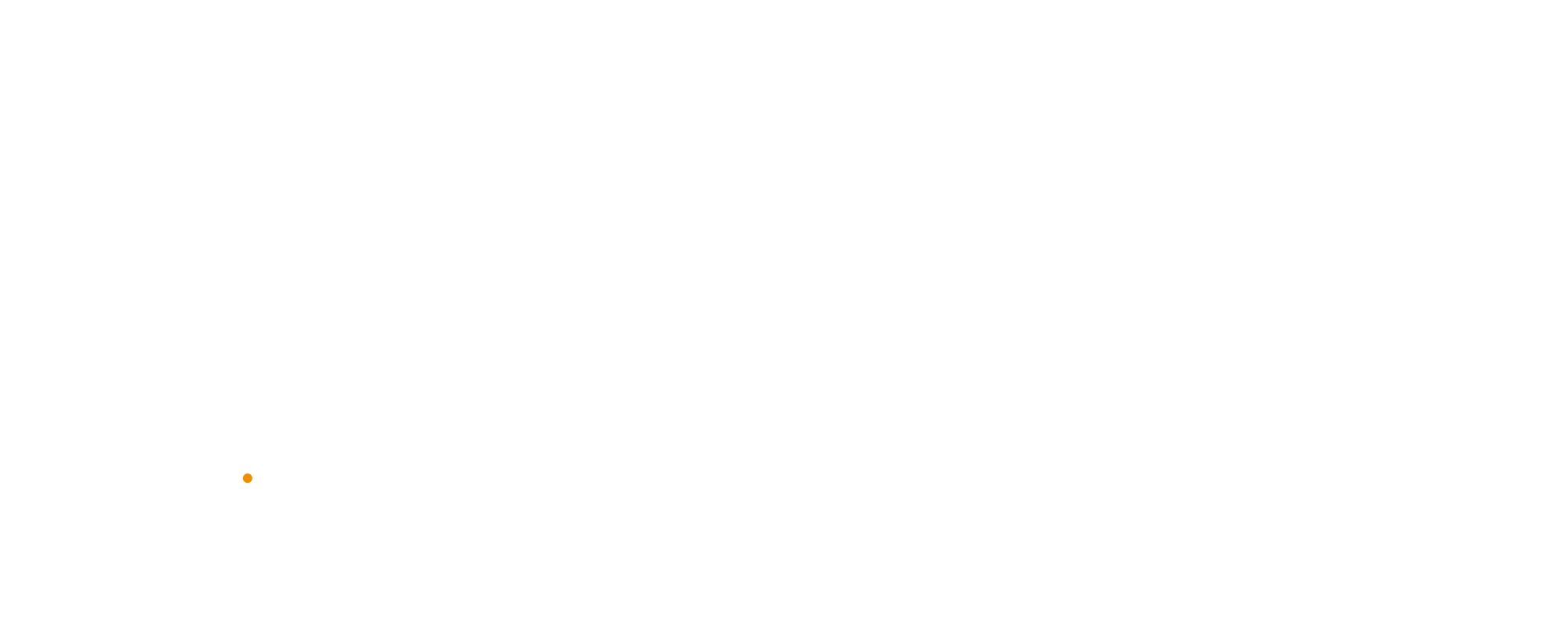
皆さんこんにちは!
SSW、更新担当の中西です
~やりがい~
アスベスト除去は、安全・法令順守・品質・スピードを同時に満たす高度な現場運用。
ここでは、発注者が本当に求めているニーズと、現場で働く人が感じるやりがいを、実務目線で整理します。
飛散ゼロ:隔離・負圧・湿潤化・清掃を“型”で回し、空気中繊維を管理。
事故ゼロ:墜落・感電・切創・熱中症を想定した安全計画。
クレームゼロ:近隣・テナントへの粉じん・臭気・騒音の抑制と告知。
違反ゼロ:事前調査・届出・資格・台帳・電子報告までの一気通貫。
手戻りゼロ:取り残し・清浄度不合格を“中間検査”で封じる。
滞留ゼロ:産廃の封入・運搬・マニフェストの迅速クローズ。
証拠で語れる安心(事前調査・作業計画・写真台帳・測定結果の即提出)
スケジュール確実性(夜間切替・部分開放・段階引渡し)
総合コスト最適(養生範囲の最適化、資機材共用、無駄な待ち時間ゼロ)
他工種との干渉ゼロ(動線分離、搬入出窓口の事前調整)
翌朝通常運転(ビル稼働のままフロア更新、エレベーター・空調連携)
緊急時の即応(負圧異常・停電・漏水時のロールバック手順)
見える安心(掲示・説明会・苦情窓口、環境測定の共有)
生活影響の最小化(搬出時間帯・車両動線・騒音配慮)
調査の精度:図面・竣工年・仕上げ層を読み、採材→分析→レベル区分を明快に。
段取り設計:隔離区画・負圧計画・三室化・湿潤化・運搬の一筆書き動線。
デジタル記録:写真台帳・差圧ログ・気中繊維測定・マニフェスト・電子報告を当日共有。
夜間・短工期対応:Go/No-Go基準とロールバック手順を台本化、翌朝の原状復帰を保証。
産廃のトレーサビリティ:封入・仮置き・運搬・処分の実績追跡がワンタッチで出せる。
事前調査・設計:疑わしい部位を洗い出し、無駄な隔離を削りつつ安全を守る最小面積設計が決まった瞬間。
施工管理:負圧・出入口・湿潤・清掃のリズムが一度も崩れず回り続ける達成感。
作業班(技能者):取り残しゼロで清浄度合格、隔離を予定どおり解除できた誇り。
環境測定・品質:データで“飛散ゼロ”を証明し、近隣からの感謝が届く喜び。
安全衛生:熱中症・有機溶剤・姿勢負荷を前倒しで潰す仕組みが効いた実感。
PM/営業:関係者が不安なく進められる台本を描き、再指名を得る手応え。
A. 事前ヒアリング10項目
竣工年/改修歴 2) 仕上げ・下地構成 3) 施工範囲・期日
稼働/夜間制約 5) 共有設備(EV/空調) 6) 近隣条件
共用部の養生要件 8) 産廃置場・動線 9) 電源/換気
報告様式・提出期限(電子報告/台帳)
B. 施工中の“4つの見える化”
差圧(負圧監視ログ)/濡れ具合(散水頻度)/清掃頻度(チェック間隔)/出入記録(人・物)
C. 解除前チェック
取り残し目視(有資格者)→試験清掃→気中繊維測定→OKなら隔離解除→写真・報告
Good(基本遵守):調査→計画→隔離・負圧→除去→清掃→測定→台帳。
Better(短工期・高信頼):+ 夜間段階引渡し、差圧の遠隔監視、近隣向け掲示・週報。
Best(大規模・複合):+ 3D/点群での養生計画、多区画同時施工の負圧バランス制御、ダッシュボードで全関係者に共有。
→ 各プランに工期・コスト・リスク低減の根拠を添えると意思決定が速い。
安全:休業災害ゼロ日数、ヒヤリ是正率、熱中症発生率
品質:気中繊維の基準内達成率、取り残し是正回数、清浄度一発合格率
工程:計画対比進捗、夜間切替の定刻復帰率、手戻り時間
コンプラ:届出/電子報告の期限遵守率、マニフェスト即日率
近隣:苦情件数、説明会参加/合意取得率
事前調査の見落とし → 仕上げ層のサンプル不足。複層採材と“グレー箇所”の暫定対策を計上。
負圧漏れ → 出入口の気密・ダクト漏れ。発煙試験と差圧ログで早期検知。
湿潤不足 → 粉じん化。噴霧量/頻度を数値基準化、乾燥部位の優先清掃。
搬出渋滞 → 共用EV競合。時間帯予約と台車隊列の標準化。
近隣不安 → 告知不足。施工前掲示+中間報告+解除報告をテンプレ化。
稼働中オフィスの夜間更新
差圧遠隔監視とロールバック台本で翌朝定刻開庁100%、苦情ゼロ。
学校の夏季改修
教室ごとに小区画化、一室一完結で清浄度一発合格、工期短縮**-12%**。
工場ライン隣接
産廃動線を外周に分離、搬出ピークの平準化で生産停止なし。
アスベスト除去の価値は、飛散ゼロを段取りで再現し、データで証明すること。
その再現性を高めるほど、不安が安心に変わり、手戻りが信頼に変わります。
今日も誰も気づかないまま、安全が保たれた。——その静かな手応えこそ、この仕事のやりがいです。
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは!
SSW、更新担当の中西です
~変遷~
耐火・断熱・防音性能の高さから、吹付材・成形板・保温材などに広範囲で利用。
しかし健康被害の知見が進むにつれ、規制の土台が整備開始。大気汚染防止法ではアスベストを「指定ばいじん」に位置づけ(1989改正)、「特別管理産業廃棄物」化(1991)で廃棄段階の管理も強化されました。環境省
廃棄物は分別・封じ込め・適正処分が前提に。
大気側も発じん作業の規制が拡充し、解体・改修現場での飛散防止が政策テーマとして前面化します。環境省+1
2005年、石綿障害予防規則(石綿則)が新設。従来の化学物質規制から独立し、作業区分・隔離・負圧・個防・計測・記録など除去作業の“型”が明確化。施行は2005年7月1日。厚生労働省+1
2006年にはアスベスト健康被害救済法が施行され、曝露被害への公的救済がスタート。厚生労働省+1
同年、政府の包括対策に基づき**「製造・使用の原則禁止」**が打ち出され、国内の新規利用に終止符(例外を除く)。環境省+1
学術・行政資料では、2012年に全面禁止が確立し、輸入品も原則禁止の運用に。以降、既存建物の解体・改修が曝露リスクの主戦場に。J-STAGE+1
2020年改正の大気汚染防止法で、全ての石綿含有建材を対象に飛散防止を強化。事前調査の義務化、都道府県等への結果報告、作業基準違反への直接罰が導入されました。環境省+1
2021年:吹付け等に加え、保温材等の除去前14日前届出、隔離解除前の有資格者による取り残し確認が義務化。ishiwata.mhlw.go.jp
2022年:石綿事前調査結果報告システムによる電子報告が本格運用。GビズID連携で労基署・自治体への同時報告が標準に。ishiwata.mhlw.go.jp+1
ルールは「守る」から**“見える化して証明する”**へ。台帳・写真・測定・電子報告が一体運用に。
工程設計:事前調査→区分判断(レベル1/2/3)→隔離・負圧→除去→清掃・封じ込め→完了確認(取り残し・清浄度)→復旧。ishiwata.mhlw.go.jp
装備・管理:負圧集じん機・HEPA、二重養生、出入口の三室化、作業員の呼吸用保護具・陰圧適合、ばく露濃度測定の平常化。ishiwata.mhlw.go.jp
記録:計画・隔離写真・作業手順・気中濃度・産廃マニフェスト・電子報告までの一気通貫の台帳。
コンサル型の事前調査・設計:図面照合・採材分析・工程別コストの最適化。
夜間・短工期の現場対応:テナント稼働中ビルで**“翌朝通常運転”**を実現する台本力。
データ主導の品質保証:測定ログ・電子報告・写真台帳で“飛散ゼロ”を見える品質に。
事前調査:設計図・竣工年・使途から疑わしき箇所の洗い出し/試料採取。結果は発注者へ説明し、規模要件に応じ電子報告。環境省+1
施工計画:区分別の隔離・負圧・湿潤化、動線・持出しルール、直接罰対象の基準を全員で共有。環境省
完了判定:取り残し確認(有資格者)→清浄度確認→隔離解除→発注者報告→記録3年保存。ishiwata.mhlw.go.jp+1
2005年の石綿則で“作業の型”が定まり、2006年の原則禁止→2012年の全面禁止で新規使用は終幕。
2020年代は事前調査・電子報告・直接罰で“見える運用”が求められる段階へ。
これからの競争力は、調査の精度・段取りの再現性・記録の即時性にあります。
「飛散ゼロを、データで証明する」——それが、次の指名につながる工事力です。
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは!
SSW、更新担当の中西です
~“止めない改修×石綿対策”~
稼働中施設の改修では、運用を止めずに安全第一で進める設計が必須。ゾーニング・夜間切替・動線分離・空気管理をベースに、利用者・近隣・従業員の安心を守りながら、確実にリスクを下げます。🔄🛡️
ゾーン分け:作業区/待機区/清浄区を視覚的に区分(掲示・カラーコード)
動線分離:作業員用シャワー・更衣・資材搬入路を専用化、利用者と交差ゼロ🚷
時間帯戦略:夜間・休校/休診日で高リスク工程を実施
情報共有:工期・騒音・搬入日を週次掲示&QRで最新情報📣
テナント営業を止めない:閉店後の瞬停工程→日中は監視・清掃中心
バックヤード搬入で来客動線から隔離
児童・生徒導線の徹底分離、掲示と見守り。屋外側の粉じん養生距離を確保。
陰陽圧管理と空気の流れを重視。救急・搬送動線は常時確保。🚑
フォークリフト動線と干渉ゼロの搬入計画。粉じんセンサで見える化📟
負圧差:電子差圧計で常時記録(アラート閾値設定)
HEPA清掃:段階清掃→白手袋テスト→最終確認
周辺監視:必要に応じ簡易粉じん計で外側もモニタリング
着工前説明会:工程・安全策・連絡先をA4一枚で配布
日々の連絡:掲示+チャット/メールで“今日の作業”“音の出る時間”を更新
クレーム一次対応:30分以内の初動連絡→原因・対策を掲示で共有⏱️
写真台帳:隔離→差圧→作業→清掃→最終確認→搬出を時系列で
差圧・運転ログ:負圧機・集じん機の稼働記録
搬出・処分:マニフェストで**“出たものの行き先”**を追跡
最終報告書:管理者・テナント・近隣説明にも使える読みやすい体裁で提出📘
夜間係数・静音機材の計上があるか🎛️
入退室ユニット・シャワー設備の仕様🧼
第三者の最終確認の扱い(必要条件の反映)
予備費:想定外部材の発見に備えた取り決め🧩
Q. 匂いは出ますか?
A. 主に養生資材・清掃剤の匂い。換気計画と無臭材選定で配慮します。
Q. どこまで“見える化”されますか?
A. 日々の掲示/差圧グラフ/写真台帳をオンライン共有。監督者がいつでも確認可能。
Q. 事故時の対応は?
A. 即時退避→封鎖→原因究明→是正のフローを訓練済み。関係者へ迅速報告します。🚨
稼働スケジュール(授業時間・診療時間・荷捌きピーク)
使えない時間帯・騒音制限・搬入制限
管理規程・入館手続き・駐車場ルール
→ 共有いただくと**“止めない工程表”**を素早く作れます。🗺️
まとめ
“安全第一×運用優先×記録の透明性”。この3点で、稼働中の施設でも止めずに安全にアスベスト対策が可能です。現場に合わせた最短・最適解を設計し、安心の引渡しまで伴走します。🤝🛡️✨
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは!
SSW、更新担当の中西です
~“安全・法令順守・見える化”~
アスベスト(石綿)対策はスピードより正確さ。私たちは事前調査→計画・届出→隔離・負圧→除去→清掃→最終確認→廃棄処理までを一貫管理し、安全・法令順守・情報公開を徹底します。DIYは絶対にNG。有資格者のチームが“見える化”で不安をゼロにします。👀✨
DIY厳禁:粉じんは目に見えず、後戻り不可。必ず専門業者へ。
法令順守:着工前の事前調査・届出、作業計画、作業環境測定、最終確認を実施。
記録の見える化:写真台帳、差圧ログ、清掃記録、搬出伝票(マニフェスト)を書面でお渡し。📒
吹付け材・保温材・耐火被覆(粉じん化しやすい)
成形板・床材・接着剤(状態や作業で粉じん化の恐れ)
古いボイラ周り・ダクト・パイプ保温 など
“リスクは材料×状態×作業で変わる”——現地での試料採取・分析が出発点です。🔬
事前調査:図面・既存記録・現地採取→分析
計画・届出:工法・工程・人員・周辺への周知、関係機関へ必要手続き📄
隔離養生・負圧管理:二重養生・専用入退室動線・負圧機+HEPAで粉じん拡散を抑制🌀
除去・封じ込め・囲い込み:有資格者が仕様に沿って安全作業
清掃・最終確認:HEPA清掃→目視→空気中濃度の確認🔍
原状復帰・廃棄処理:密閉梱包→適正運搬→最終処分(マニフェストで追跡)🚚
工程は夜間・休業日にも対応。騒音・粉じん・動線を運用優先で設計します。🌙
人の安全:全面マスク・使い捨て防護服・二次感染防止の入退室手順
環境の安全:負圧差モニタリング、エアロゾル拡散のゼロ化設計
品質の確証:写真台帳・作業日報・最終確認の結果を書面で保管🗂️
事前調査・分析の範囲(採取点数・報告書の有無)
隔離養生の仕様(二重養生/人荷動線/負圧機の台数とHEPA)
作業員資格・人数・工程(夜間分割の可否)
最終確認(空気中濃度の確認方法/第三者検査の取り扱い)
廃棄物の管理(梱包方法・運搬・マニフェスト)
引渡し書類(写真台帳・差圧ログ・報告書一式)📘
Q. どれくらいの期間が必要?
A. 規模・建材・運用条件で変動。調査→届出→施工の順に最短経路で組み立てます。
Q. 近隣への影響は?
A. 事前周知・動線分離・負圧管理で外部への飛散を防止。必要に応じ夜間施工で騒音配慮。
Q. 追加費用が出るのは?
A. 想定外の建材や範囲拡大が主因。調査の精度が追加の抑止に直結します。🔎
住所/建物用途・築年/図面・改修履歴
予定工期・営業/居住の制約(止めたくない時間帯)
近隣状況(店舗・学校・病院など)
→ これだけで初期プラン・概算・工程をご提示できます。🗓️
まとめ
“正しく調べ、正しく封じ、正しく処分する”。この三段ロジックで、不安のないアスベスト対策を実装します。私たちが安全と手続きを丸ごと伴走します。🛡️🤝
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは!
SSW、更新担当の中西です
前回に引き続き、アスベストについての基本をお届けしています😊
今回は、「アスベストってどんな場所に使われていたの?」という疑問にお答えしていきます。
アスベストが広く使われたのは、高度経済成長期(昭和30〜50年代)から平成初期にかけての建物です。この時期は日本中でビルや施設がどんどん建てられた時代。
耐火性・断熱性に優れていたアスベストは、**“建材の定番”**として、さまざまな現場で使われていました。
アスベストは以下のような場所に使われていることが多くあります👇
天井や壁の吹き付け材
→ 災害時の延焼を防ぐために使用されましたが、今では最も飛散リスクの高い箇所です。
パイプやダクトの保温材(特にボイラー室や機械室)
→ 高温の配管や蒸気設備に巻き付ける形で使用されていました。
屋根や外壁のスレート材・波板
→ 軽くて加工しやすいため、工場や倉庫などでよく見られます。
間仕切り壁や床下の断熱材
→ 目に見えにくい場所にも潜んでいる可能性があるため、注意が必要です。
電気設備の絶縁材や火気設備周辺の耐火材
→ 火に強い性質を活かして、スイッチボックスや分電盤まわりにも使用されていました。
とくにアスベスト使用の頻度が高かったのが、以下のような建物です。
公共施設(市役所・体育館・文化ホールなど)
工場・倉庫・プラント設備
学校や病院
昭和〜平成初期に建てられた集合住宅や商業施設
こういった建物は老朽化による解体・リフォームが進む時期に入っており、アスベストの有無を調べる「事前調査」が非常に重要となってきています。
もし、アスベストが使われている建材を知らずに壊したり削ったりしてしまうと…
目に見えない細かな繊維が空気中に飛び散り、作業員や住民が吸い込んでしまうリスクがあります。
だからこそ、解体や改修工事の前には必ず【専門調査】が必要なんです。
次回は、その「事前調査ってどんなことをするの?」というテーマで、現場での調査方法や流れをくわしくご紹介します🧪📋
建物を安全に守るために、正しい知識を少しずつ身につけていきましょう!
次回もお楽しみに!
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは!
SSW、更新担当の中西です。
当ブログにお越しいただき、ありがとうございます😊
今回は「アスベストって最近よく聞くけど、実際どんなものなの?」という方に向けて、やさしく解説していきます。
アスベストとは、**「石綿(いしわた)」**と呼ばれる天然の鉱物繊維のことです。
実はとっても細かい繊維でできていて、耐熱性・耐久性・絶縁性・防音性などに優れているため、昭和の建物では“万能素材”として重宝されていました。
たとえばこんな場所に使われてきました👇
屋根材や外壁材
天井の吹き付け材
配管の保温材
ボイラーや電気機器の断熱材
軽くて丈夫で加工しやすく、コストも安かったことから、学校、病院、ビル、工場…といった多くの建物で利用されてきたんです。
そんな便利なアスベストですが、健康への影響が非常に大きいということで、現在では大問題になっています。
アスベストの繊維は髪の毛よりもずっと細く、空気中に舞い上がると、目には見えないほど微細な粒子となって体内に入り込みます。そして、長い年月をかけて肺に蓄積し、以下のような病気を引き起こすリスクがあります。
中皮腫(ちゅうひしゅ)
肺がん
アスベスト肺(じん肺の一種)
これらは**“20年〜40年”という長い潜伏期間**ののちに発症することがあり、「静かな時限爆弾」とも呼ばれています。
はい。現在、日本ではアスベストの製造・輸入・使用はすべて禁止されています。
しかし、古い建物や設備には今もアスベストが残っている可能性があり、知らずに解体したり穴を開けたりすると、繊維が飛散してしまう危険性があります。
だからこそ、建物の改修や解体を行うときには、専門の調査・除去作業が必要なんです。私たちのような専門業者が、正しい知識と技術で安全に取り扱うことが求められています。
次回もお楽しみに!
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは!
SSW、更新担当の中西です。
今回は、アスベスト除去工事の“これから”について一般的な市場での例を基にご紹介します。
高齢化する建物、増える老朽インフラ、そして深刻化する人材不足…。
アスベスト除去のニーズは今後ますます増える一方、対応できる人材と技術は追いついていません。
でも、未来は暗いわけではありません。
技術と制度の進化が、未来の除去工事を大きく変えようとしています。
現場の粉塵濃度をリアルタイムで測定し、基準を超えた場合は自動でアラーム発報&作業中断。
AIが作業スピードや湿潤度を計算し、最適な作業条件を提案する未来もすぐそこに。
現在、一部の特殊解体業者では、遠隔操作型ロボットによるアスベスト除去の試験運用が始まっています。
人が入りづらい狭小空間や高所でも安全に作業可能
飛散リスクを最小限に抑えながら、均一で正確な剥離が実現
作業者の曝露リスクも激減
解体をせずとも、アスベストの飛散を完全に抑えるための封じ込め材やコーティング剤が進化しています。
吹付アスベストを固定化し、粉塵化を防止
作業が難しい場合の簡易・低コスト対策として注目
目視では分からない建材のアスベスト含有の有無を、高精度赤外線スキャナーや蛍光X線分析機器で素早く確認できる技術も登場。
工期短縮・コスト削減・飛散リスクの低減に貢献しています。
2022年のアスベスト法改正により、すべての解体・改修工事でアスベスト調査が義務化されました。
これにより、「知らずに工事をしてしまう」リスクが大幅に軽減されました。
さらに今後は:
電子届出システムの普及(電子申請化)
作業報告の義務化・映像記録の提出
除去技術者の国家資格化の議論も進行中
高校・専門学校でのカリキュラム導入
ICTとVRによる安全教育
熟練職人の技術継承を“デジタル化”で保存し、若手に引き継ぐ取り組みも始まっています。
私たちが今日アスベストを除去するということは、
未来の子どもたちに、安全で清潔な空間を残すことにほかなりません。
除去技術は進化し、制度は強化され、社会の理解も少しずつ深まってきました。
これからのアスベスト対策は、「危険をなくす」だけでなく、未来の暮らしを守る希望の技術として輝いていくでしょう。
次回もお楽しみに!
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは!
SSW、更新担当の中西です。
今回は、私たちが日々取り組んでいるアスベスト除去工事と環境問題についてお話しします。
かつて「夢の素材」と呼ばれたアスベスト。しかし、現在ではその健康被害と環境リスクの象徴とも言える存在です。
そして今もなお、私たちの身の回りにはその“名残”が数多く残っているのが現実です。
アスベスト(石綿)は、天然鉱物由来の繊維状物質で、耐火性・絶縁性・強度・防音性に優れていたため、かつては建築資材や工業製品に幅広く使用されていました。
吹付け材(鉄骨・天井裏)
耐火被覆材・断熱材・保温材
スレート屋根、外壁材、タイル接着剤 など
アスベストが環境問題になる主な理由は以下のとおりです:
空中飛散:除去・解体中に繊維が空中に舞うと、周囲の人や自然環境に拡散。
人体への影響:吸引すると肺がん、中皮腫、石綿肺などを引き起こす可能性。
廃棄処理の困難さ:通常の産業廃棄物とは違い、特別管理産業廃棄物として厳重に扱う必要があります。
アスベスト除去工事では、環境保全のために厳格な作業基準が求められます。以下が代表的なポイントです。
負圧隔離(HEPAフィルター付き集塵機)
養生シート二重張り
湿潤化処理(石綿が飛ばないように濡らす)
作業員は防護服・マスク・呼吸保護具を着用
現場周囲には掲示板・立ち入り禁止区画を明示
作業終了後は作業場内の徹底清掃と気中濃度測定
除去したアスベスト含有物は、専用の耐水性二重袋に密封し、マニフェスト(管理伝票)により適正処理場へ搬出します。
非公開・違法除去のリスク:一部では、無届けや無資格の工事が横行し、飛散・不法投棄の問題が発生しています。
管理体制の地域格差:自治体により届出・監視の厳しさが異なり、基準の統一が求められています。
費用負担の大きさ:除去工事は高コストのため、所有者が工事を先送りするケースも。
アスベスト除去工事は、単なる“解体作業”ではなく、人の命と環境を守る重要なミッションです。
目に見えない有害物質と日々向き合いながら、私たちは「安心できる空間」を次の世代に残すための責任を担っています。
次回は、アスベスト除去工事の未来の展望と技術革新について、詳しく解説します!
次回もお楽しみに!
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは!
SSW、更新担当の中西です。
今回は、アスベスト除去工事の現場で最も大切にされている「鉄則」について解説します。
アスベスト除去は、普通の解体工事とは一線を画す特殊作業。
**「粉じん=命に関わる」**という認識のもと、作業は一つひとつが命を守る行動でなければなりません。
では、現場で守るべき“5つの鉄則”を順に見ていきましょう。
工事の前には、必ず建物のアスベスト含有調査を行います。
使用されている建材の種類・使用場所・面積・形状を正確に把握
「アスベストあり」と判定された場合は、レベル1〜3のリスク区分を行い、除去方法を選定
調査結果は、労働基準監督署や自治体へ法定の届け出を行う義務
「知らなかった」「見落とした」は許されない。
事前調査こそ、すべての安全管理の出発点です。
除去工事の現場では、アスベストの飛散を絶対に外部へ漏らさないための“養生”が命綱です。
壁・天井・床・出入口をビニールシートで完全密閉
HEPAフィルター付きの負圧除じん装置で、常に作業場内の気圧を低く保つ
作業者の出入り口にはエアシャワー付きの前室(グローブボックス)を設置
作業員が出入りするたびにチリ1つ持ち出さない仕組みをつくることが鉄則です。
作業者が身にまとう装備も、**文字通り「命を守る防具」**です。
専用の防護服(ツナギ型)、使い捨てマスク(P100以上推奨)、ゴーグル、手袋、靴カバー
使用後の防具類はすべて密封して産業廃棄物として廃棄処理
作業時間・休憩時間を管理し、長時間暴露を避けるスケジュール管理も必要
健康診断・粉じん作業歴の管理も含めて、安全衛生管理がすべてのベースです。
アスベスト工事は、近隣住民や関係者への説明責任が非常に重要です。
事前に説明会や通知書を通じて「なぜアスベスト除去が必要なのか」を説明
工事中の騒音・臭気・飛散防止の対策を明示
看板・バリケードでの明確な表示、作業時間の調整なども配慮
「見えない危険」だからこそ、“見える安心”を提供する姿勢が信頼を生みます。
除去作業が完了したら、それで終わりではありません。
作業区域内の**アスベスト繊維濃度測定(空気サンプル)**を実施
0.01本/cm³以下という厳しい基準をクリアするまで再清掃・再測定を繰り返す
最終的に「アスベスト飛散なし」と第三者機関の認定を得て工事完了
「見えない安全」を科学的根拠と証拠で残すことが信頼につながります。
この工事は、目に見えないリスクと常に向き合う、極めて責任の重いプロフェッショナルの仕事です。
だからこそ、現場のすべての判断と作業が「命を守るための鉄則」に基づいて動いています。
私たちはこれからも、過去の過ちを教訓に、安心・安全な未来を築くために丁寧な仕事を続けていきます。
次回もお楽しみに!
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは!
SSW、更新担当の中西です。
今回は、「アスベスト除去工事の歴史」についてお話しします。
かつては「奇跡の鉱物」としてもてはやされたアスベスト(石綿)。その後、健康被害が明らかになり、現在では厳重な管理と除去が必要な有害物質となりました。
では、このアスベストが社会でどのように扱われてきたのか、除去工事がどう進化してきたのか、その歴史を見ていきましょう。
アスベストは耐熱性・耐摩耗性・絶縁性に優れ、加工しやすい特徴から、20世紀前半〜高度経済成長期にかけて建材として大活躍しました。
建築物の吹付け材、断熱材、耐火被覆材、波板スレート、ボイラー周りなど、あらゆる分野で使用
特に1955年〜1985年頃までに建てられた多くの学校・病院・工場・公共施設に使用実績あり
当時は「安価で万能な素材」として重宝されていました。
徐々に、アスベストを扱った作業員や住民に、深刻な健康被害が確認されるようになりました。
アスベストの繊維が肺に入り込み、石綿肺・中皮腫・肺がんなどを引き起こすことが判明
潜伏期間が20〜40年と長く、症状が出た頃には手遅れになるケースが多発
1987年:国際がん研究機関が「アスベストは確実な発がん物質」と認定
これを受け、社会全体で「アスベストをどう扱うか?」が大きな課題となりました。
日本では段階的にアスベストの使用が制限されていきました。
1995年:吹付けアスベストの使用が原則禁止
2006年:一部の例外を除き、アスベストを含む建材の製造・使用が全面禁止
2012年:建築物等の解体・改修時にアスベスト使用の有無調査が義務化
こうして、新たなアスベスト使用は原則ゼロに。しかし、過去に使用された建物が残っているため、「除去工事」は今もなお、社会的に重要な作業とされています。
現在では、アスベスト除去工事は高い専門性と厳重な安全対策が求められる仕事です。
厚生労働省の指導に基づいた作業基準と届出義務
除去・封じ込め・囲い込みといった工法の選択
作業員の防護服・マスク着用、負圧養生、飛散防止処理の徹底
作業完了後は空気中のアスベスト濃度測定と第三者機関による検査
「見えない粉じん」が命に関わるからこそ、作業の一つひとつに高い倫理と責任感が求められます。
アスベスト除去は、かつての無知や経済優先の中で広がった素材の“後始末”とも言える作業です。
しかし、その工事は今、未来の健康と安心を守るための希望の仕事でもあります。
次回は、そんなアスベスト除去工事において、現場で守られている“鉄則”についてお話しします。
次回もお楽しみに!
お問い合わせは↓をタップ