-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
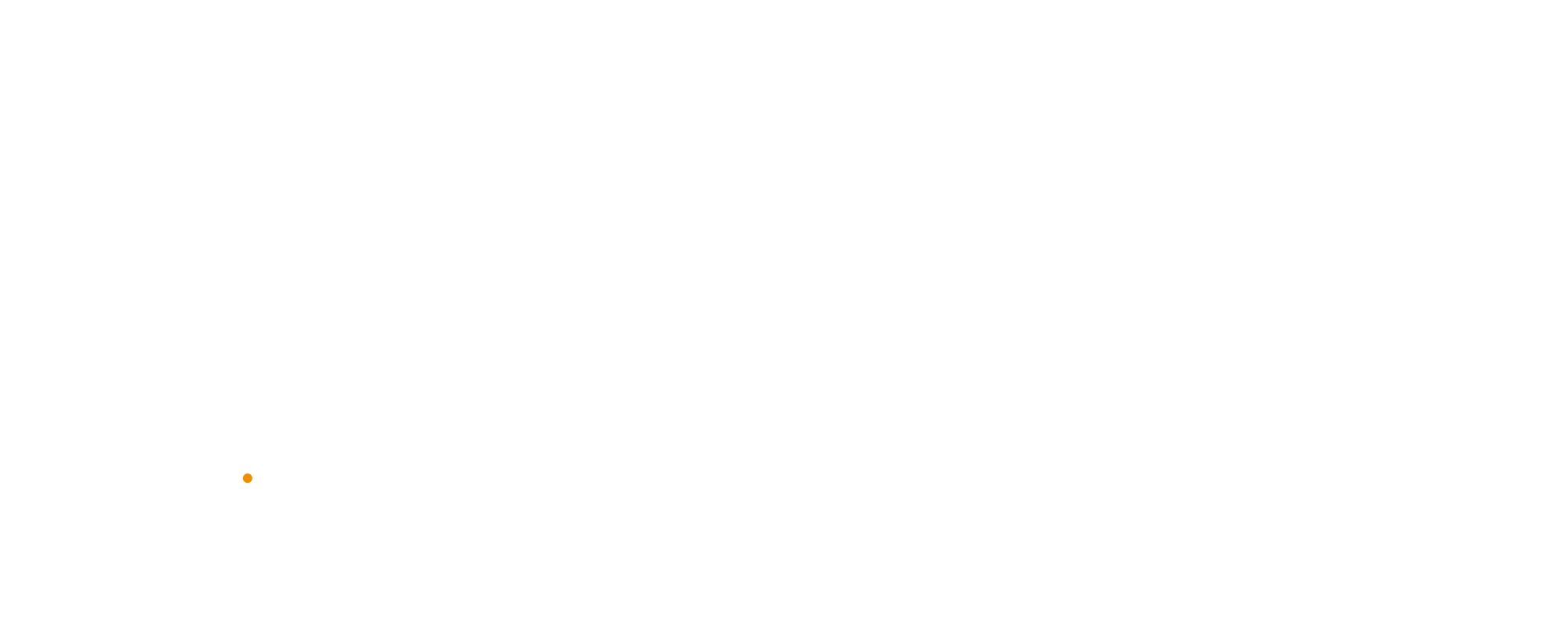
皆さんこんにちは!
SSW、更新担当の中西です。
今回は、アスベスト除去工事の“これから”について一般的な市場での例を基にご紹介します。
高齢化する建物、増える老朽インフラ、そして深刻化する人材不足…。
アスベスト除去のニーズは今後ますます増える一方、対応できる人材と技術は追いついていません。
でも、未来は暗いわけではありません。
技術と制度の進化が、未来の除去工事を大きく変えようとしています。
現場の粉塵濃度をリアルタイムで測定し、基準を超えた場合は自動でアラーム発報&作業中断。
AIが作業スピードや湿潤度を計算し、最適な作業条件を提案する未来もすぐそこに。
現在、一部の特殊解体業者では、遠隔操作型ロボットによるアスベスト除去の試験運用が始まっています。
人が入りづらい狭小空間や高所でも安全に作業可能
飛散リスクを最小限に抑えながら、均一で正確な剥離が実現
作業者の曝露リスクも激減
解体をせずとも、アスベストの飛散を完全に抑えるための封じ込め材やコーティング剤が進化しています。
吹付アスベストを固定化し、粉塵化を防止
作業が難しい場合の簡易・低コスト対策として注目
目視では分からない建材のアスベスト含有の有無を、高精度赤外線スキャナーや蛍光X線分析機器で素早く確認できる技術も登場。
工期短縮・コスト削減・飛散リスクの低減に貢献しています。
2022年のアスベスト法改正により、すべての解体・改修工事でアスベスト調査が義務化されました。
これにより、「知らずに工事をしてしまう」リスクが大幅に軽減されました。
さらに今後は:
電子届出システムの普及(電子申請化)
作業報告の義務化・映像記録の提出
除去技術者の国家資格化の議論も進行中
高校・専門学校でのカリキュラム導入
ICTとVRによる安全教育
熟練職人の技術継承を“デジタル化”で保存し、若手に引き継ぐ取り組みも始まっています。
私たちが今日アスベストを除去するということは、
未来の子どもたちに、安全で清潔な空間を残すことにほかなりません。
除去技術は進化し、制度は強化され、社会の理解も少しずつ深まってきました。
これからのアスベスト対策は、「危険をなくす」だけでなく、未来の暮らしを守る希望の技術として輝いていくでしょう。
次回もお楽しみに!
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは!
SSW、更新担当の中西です。
今回は、私たちが日々取り組んでいるアスベスト除去工事と環境問題についてお話しします。
かつて「夢の素材」と呼ばれたアスベスト。しかし、現在ではその健康被害と環境リスクの象徴とも言える存在です。
そして今もなお、私たちの身の回りにはその“名残”が数多く残っているのが現実です。
アスベスト(石綿)は、天然鉱物由来の繊維状物質で、耐火性・絶縁性・強度・防音性に優れていたため、かつては建築資材や工業製品に幅広く使用されていました。
吹付け材(鉄骨・天井裏)
耐火被覆材・断熱材・保温材
スレート屋根、外壁材、タイル接着剤 など
アスベストが環境問題になる主な理由は以下のとおりです:
空中飛散:除去・解体中に繊維が空中に舞うと、周囲の人や自然環境に拡散。
人体への影響:吸引すると肺がん、中皮腫、石綿肺などを引き起こす可能性。
廃棄処理の困難さ:通常の産業廃棄物とは違い、特別管理産業廃棄物として厳重に扱う必要があります。
アスベスト除去工事では、環境保全のために厳格な作業基準が求められます。以下が代表的なポイントです。
負圧隔離(HEPAフィルター付き集塵機)
養生シート二重張り
湿潤化処理(石綿が飛ばないように濡らす)
作業員は防護服・マスク・呼吸保護具を着用
現場周囲には掲示板・立ち入り禁止区画を明示
作業終了後は作業場内の徹底清掃と気中濃度測定
除去したアスベスト含有物は、専用の耐水性二重袋に密封し、マニフェスト(管理伝票)により適正処理場へ搬出します。
非公開・違法除去のリスク:一部では、無届けや無資格の工事が横行し、飛散・不法投棄の問題が発生しています。
管理体制の地域格差:自治体により届出・監視の厳しさが異なり、基準の統一が求められています。
費用負担の大きさ:除去工事は高コストのため、所有者が工事を先送りするケースも。
アスベスト除去工事は、単なる“解体作業”ではなく、人の命と環境を守る重要なミッションです。
目に見えない有害物質と日々向き合いながら、私たちは「安心できる空間」を次の世代に残すための責任を担っています。
次回は、アスベスト除去工事の未来の展望と技術革新について、詳しく解説します!
次回もお楽しみに!
お問い合わせは↓をタップ